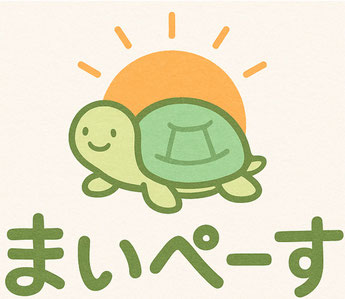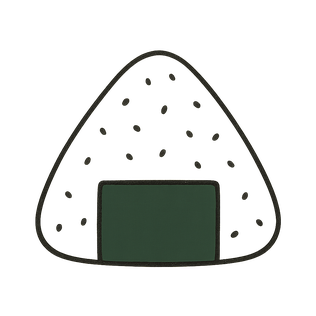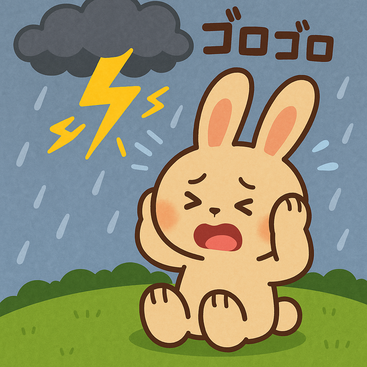知識・雑学
知識・雑学 · 06日 10月 2025
秋になるとよく耳にする「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」。 きれいな満月を見上げながら「今日は十五夜だね」と話す方も多いのではないでしょうか。 でも、“中秋”ってどういう意味なのでしょう? “中秋”とは“秋のまんなか” 昔の日本では、今のカレンダー(新暦)ではなく“旧暦”を使っていました。...
知識・雑学 · 04日 10月 2025
「食欲の秋」「読書の秋」と並んでよく聞くのが「スポーツの秋」。 でも、なぜ10月になると「スポーツの秋」と呼ばれるのでしょうか? 気候がちょうどいいから 夏の暑さがやわらぎ、冬の寒さもまだ遠い10月は、体を動かすのにぴったりの季節です。 走ったり外で遊んだりしても汗をかきすぎず、快適に運動できます。 まさに「体を動かしたくなる秋」なんですね。...
知識・雑学 · 03日 10月 2025
10月の別名を「神無月(かんなづき)」といいます。 「神様がいなくなる月」という意味ですが、ちょっと不思議ですよね。 実はこの呼び名には、日本ならではの言い伝えがあるのです。 出雲に集まる神様たち 昔から、日本の神様たちは10月になると出雲大社(いずもたいしゃ/島根県)に集まるといわれています。...
知識・雑学 · 27日 9月 2025
学校や塾で毎日のように使うシャーペン。 芯の種類を見てみると「HB」が一番多いですよね。 では、どうしてHBが“標準”になっているのでしょうか? 芯の濃さと硬さ シャーペンや鉛筆の芯には、BやHなどの表記があります。 B(Black)はやわらかくて濃い H(Hard)はかたくて薄い その真ん中にあるのが「HB」です。 ちょうどいいから“標準”に...
知識・雑学 · 25日 9月 2025
勉強をしていると「間違えちゃいけない」と思いがちですよね。 でも実は、歴史に名を残した偉人たちだって、たくさんの“失敗”をしています。 その失敗があったからこそ、新しい道が開けたことも多いのです。 ⚔ ナポレオンの失敗 フランスの英雄ナポレオンは、戦いに強いイメージがあります。...
知識・雑学 · 19日 9月 2025
毎日の食事の前に言う「いただきます」。 何気なく口にしている言葉ですが、実はとても深い意味があるのをご存じですか? 命をいただくという意味 「いただきます」は、食べ物の“命”をいただくことへの感謝の言葉です。 ごはんや野菜、お肉や魚には、もともと命がありました。 それを食べることで、私たちは生きていく力をもらっているのです。...
知識・雑学 · 18日 9月 2025
明日から少し涼しくなるとは言われておりますが、まだまだ暑い日が続きますね。 今はエアコンや扇風機があるので快適に過ごせますが、昔の人たちはどうやってこの暑さをしのいでいたのでしょうか? 実は、日本には昔から夏を涼しく過ごすための工夫がたくさんあったのです。 打ち水(うちみず) 江戸時代から行われていたのが「打ち水」。...
知識・雑学 · 17日 9月 2025
夏休みが終わっても、まだまだ暑い日が続きますね。 この時期によく耳にする言葉が「残暑(ざんしょ)」。 では、この「残暑」とは、いつまでを指すのでしょうか? 暦の上では「立秋」から秋 実は、日本の暦の上では8月7日ごろの「立秋」から秋になります。 でも、実際にはその頃が一年で一番暑い時期…。...
知識・雑学 · 13日 9月 2025
お弁当やコンビニでよく食べるおにぎり。 丸い形や俵型もありますが、やっぱり一番多いのは「三角のおにぎり」ですよね。 では、どうしておにぎりは三角形が多いのでしょうか? ✋ 手で持ちやすいから 三角形のおにぎりは、手のひらにぴったり収まります。 持ちやすく、食べやすい形だからこそ、今でも三角形が定番になっているのです。...
知識・雑学 · 12日 9月 2025
夏や秋の夕方、空に光がピカッと光ったかと思うと、「ゴロゴロゴロ〜!」と大きな音が響きます。 ちょっと怖いけれど、気になる雷。どうしてあんなふうに長くゴロゴロと響くのでしょうか? 雷の音の正体は? 雷の音は「空気が一気に膨らんで起こる音」です。 雷の電気はとても強く、周りの空気を一瞬で数千度にも熱します。...