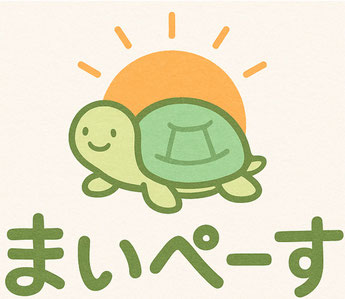「うちの子、宿題は出してるんですけど…テストになるとできてなくて」
「ノートは埋まってるのに、内容は覚えていないみたいで…」
まいぺーすに通う保護者の方から、よくそんな声をいただきます。
実は、宿題は“出すためにやるもの”ではなく、“身につけるために使うもの”。
やり方を少し変えるだけで、ぐんと学習効果が高まるんです。
今回は、まいぺーすで実践している「身につく宿題のやり方」をご紹介します。
■ 「とりあえず終わらせる」ではもったいない
学校から出される宿題は、授業の内容を定着させるための大切なもの。
でも、「急いで写すだけ」「考えずに書き写すだけ」では、せっかくの時間が“作業”で終わってしまいます。
■ まいぺーすの宿題サポートの工夫
①「どこがわからないか」に気づけるように
まいぺーすでは、宿題をただ終わらせるだけでなく、「どこがわからなかったか」「なぜ間違えたか」を一緒に確認しています。
「わからなかったところをチェックしてOK」など、ふり返りの習慣をつけていきます。
② 量より“考えた時間”を大切に
苦手な問題を5分間考えたことは、大量のドリルよりも価値があります。
「時間がかかったけど、わかった!」という経験が、自信と理解につながるのです。
③「できた!」を一緒に喜ぶ
「宿題が終わったね」ではなく、「今日は○○が自分で解けたね!」と、できたことを一緒に喜ぶことが、子どものやる気につながります。
■ 保護者の方へのお願い
宿題に時間がかかっても、うまくいかない日があっても大丈夫です。
大切なのは、「できるようになろうとしている」気持ちを受け止めること。
「ちゃんと見てるよ」「今日もよくがんばったね」という声かけが、お子さまの安心と成長を支える土台になります。
まいぺーすでは、ひとつひとつの小さな「できた」を見逃しません。
だからこそ、宿題の“質”を変えることがポイントです。
まとめ
宿題は「ただ終わらせるもの」ではなく、「理解を深め、自信を育てる道具」。
まいぺーすでは、一人ひとりに合わせて、「宿題のやり方」も一緒に学んでいけるようサポートしています。
「毎日の宿題、うまく取り組めているかな?」
「どう声をかければいい?」
そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。