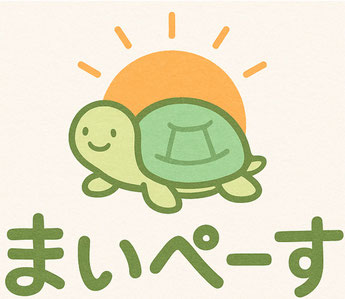「うちの子、勉強がきらいみたいで…」
「ノートも開かないし、机に向かおうともしなくて…」
ご相談に来られる保護者の方から、よく伺うお悩みです。
でも、私たちは思うのです。本当に“勉強がきらい”な子なんて、いないのかもしれない。
■ 「きらい」の奥にある“ことばにならない気持ち”
子どもたちの「勉強きらい」という言葉の奥には、実はいろんな気持ちが隠れています。
-
「わからないのが恥ずかしい」
-
「できないと思われたくない」
-
「がんばってもどうせムダって思われそう」
-
「前に失敗してイヤな思いをした」
こういった経験が積み重なると、「やらない」ことが自分を守る手段になってしまうこともあります。
■ 苦手=能力の問題ではない
私たちがたくさんの生徒を見てきた中で確信していること。
それは、“苦手”は能力の差ではなく、「タイミング」と「環境」で変わるということです。
・少しだけ難しすぎた
・説明のされ方が自分に合っていなかった
・不安な気持ちが強くて集中できなかった
そんな“つまずきの種”が、苦手意識の芽になってしまうことはよくあります。
■ まいぺーすでは、まず「安心」から始めます
「どこからわからないの?」と聞かれても、すぐに答えられる子は少ないもの。
まいぺーすでは、まずその子の話をじっくり聞くことからスタートします。
「わからない」を責めない。
「前に進もうとしていること」自体を、認めていく。
そうすることで、少しずつ心の中の“勉強きらい”がやわらいでいくのです。
■ 小さな「できた」が、気持ちを変える
1問だけ正解した。
自分から「もう1問やってみよう」と言った。
声は出さなかったけど、うなずいてくれた。
そんな小さな「できた!」を積み重ねていくうちに、子どもたちの表情や言葉に、少しずつ変化が現れていきます。
まとめ
「勉強がきらい」は、責められることではありません。
それは、まだ「自分に合った学び方」や「安心して取り組める場所」に出会えていないだけかもしれないのです。
まいぺーすは、どんなスタート地点の子でも大歓迎です。
「勉強がきらい」から「ちょっと好きかも?」に変わる、その一歩を一緒に見つけていきましょう。