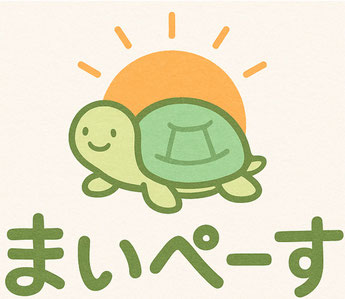今の子どもたちにとって「夏休み」は当たり前の長期休暇。
でも、昔の日本――江戸時代の子どもたちには、今のような夏休みはあったのでしょうか?
🌿 江戸の“寺子屋”には長い休みはなかった?
江戸時代、子どもたちは「寺子屋」という学びの場に通っていました。
寺子屋は今の学校に近い存在ですが、実は長い夏休みのような制度はなかったといわれています。
ただし、真夏の暑い時期やお盆の時期には、自然とお休みが取られることも多かったそうです。
農作業を手伝う家庭では、勉強よりも家の仕事が優先されることもありました。
☀️ 遊びと学びが一体だった暮らし
江戸の子どもたちは、遊びながら学ぶことも多くありました。
たとえば、
-
川遊びを通じて自然と水の扱いを覚える
-
商家の子どもは店先でそろばんや読み書きを身につける
-
お祭りや行事の準備を手伝いながら地域のつながりを学ぶ
今の「夏休みの自由研究」に近い体験が、生活そのものに組み込まれていたといえます。
🌸 今に通じる“夏の学び”
江戸の子どもたちにとっては、長い休みこそありませんでしたが、生活や季節そのものが学びの場でした。
現代の子どもたちにとっても、夏の体験(花火、祭り、旅行、自然の観察など)は大切な学びになります。
「夏休みの宿題」と聞くと大変そうに思えるけれど、江戸の子どもたちと同じように、日々の暮らしの中での気づきや体験が、実は一番の学びなのかもしれません。