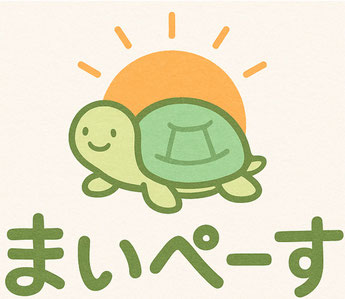明日から少し涼しくなるとは言われておりますが、まだまだ暑い日が続きますね。
今はエアコンや扇風機があるので快適に過ごせますが、昔の人たちはどうやってこの暑さをしのいでいたのでしょうか?
実は、日本には昔から夏を涼しく過ごすための工夫がたくさんあったのです。
打ち水(うちみず)
江戸時代から行われていたのが「打ち水」。
家の前や道に水をまくことで、地面の熱を冷まし、風が通ると涼しく感じられる工夫です。
今でも夏の風物詩として続いていますね。
風鈴(ふうりん)
チリンチリンと鳴る風鈴の音は、実際に温度を下げるわけではありません。
でも「音を聞くと涼しい気分になる」という日本人の感覚を大切にした暮らしの知恵です。
心理的な効果で、暑さを和らげていたのです。
よしずやすだれ
昔の家には、窓や縁側に「よしず」や「すだれ」を立てかけていました。
直射日光を防ぎながら風を通すことで、部屋を涼しく保つことができました。
自然の素材を使った、エコな暑さ対策ですね。
夏の食べ物の工夫
そうめんや麦茶など、体を冷やす食べ物や飲み物も昔から親しまれてきました。
食べ物でも涼をとる工夫がされていたのです。
まとめ
-
打ち水で地面の熱を冷ます
-
風鈴の音で涼を感じる
-
よしずやすだれで日差しをやわらげる
-
食べ物や飲み物でも体を冷やす
昔の人の暮らしの知恵は、今でも役立つものばかり。
残暑の厳しい今こそ、ちょっと取り入れてみると涼しく過ごせるかもしれませんね。