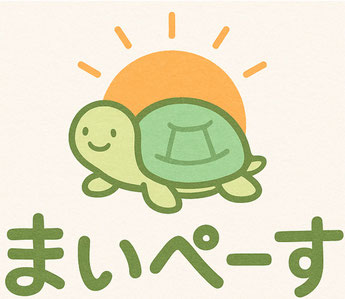10月になると、制服や服装を切り替える「衣替え」をする学校が多いですよね。
朝晩は涼しいけれど、昼間はまだ少し暑い…。
そんな季節にどうして衣替えが習慣になったのでしょうか?
衣替えのはじまり
衣替えの習慣は、平安時代にまでさかのぼります。
宮中では夏と冬で服を着替える決まりがあり、それが少しずつ庶民にも広まっていきました。
江戸時代には、幕府が「6月1日と10月1日に衣替えをする」と定め、社会全体に根づいていったのです。
気候と暮らしの知恵
日本は四季のある国。
暑さや寒さに合わせて服を替えることは、健康を守るためにも欠かせませんでした。
特に昔は冷暖房がないため、衣替えは体調管理の大切な工夫だったのです。
今の学校でも続く理由
今でも多くの学校で6月と10月に衣替えをします。
一斉に切り替えることで「季節の変わり目」を意識でき、子どもたちにとっても節目になります。
また、服装を揃えることで生活リズムや気持ちを新しくする効果もあるのです。
まとめ
-
衣替えは平安時代からの習慣
-
日本の四季と健康を守る暮らしの知恵
-
学校での衣替えは、節目を感じる大切な行事
10月は新しい季節のスタート。
衣替えをきっかけに、生活や勉強のリズムも気持ちよく整えていきたいですね。