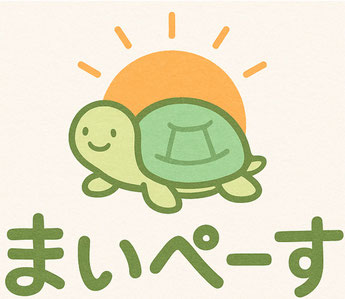10月の別名を「神無月(かんなづき)」といいます。
「神様がいなくなる月」という意味ですが、ちょっと不思議ですよね。
実はこの呼び名には、日本ならではの言い伝えがあるのです。
出雲に集まる神様たち
昔から、日本の神様たちは10月になると出雲大社(いずもたいしゃ/島根県)に集まるといわれています。
全国の神様が一か所に集まるため、他の地域には神様がいなくなってしまう――それが「神無月」と呼ばれる理由なのです。
出雲では“神在月”
一方で、神様を迎える出雲の地域では、逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれています。
同じ10月でも呼び方が違うのは面白いですね。
神様は何をしているの?
出雲に集まった神様たちは、人々の縁(えん)について話し合っているといわれています。
結婚や人間関係、出会いなど…神様どうしが相談して決めるのだそうです。
昔の人々は、こうした言い伝えを通して季節を感じたり、生活の中に神様の存在を思い描いてきました。
まとめ
-
10月は「神無月」と呼ばれる
-
神様が出雲大社に集まるため、全国からいなくなると考えられていた
-
出雲地方では「神在月」と呼ばれる
-
神様は人の縁を話し合っていると伝えられている
普段の生活ではあまり意識しない“神無月”。
言葉の背景を知ると、10月をちょっと特別に感じられますね。