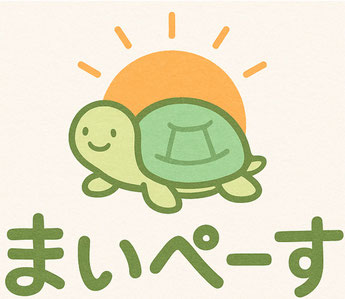秋になるとよく耳にする「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」。
きれいな満月を見上げながら「今日は十五夜だね」と話す方も多いのではないでしょうか。
でも、“中秋”ってどういう意味なのでしょう?
“中秋”とは“秋のまんなか”
昔の日本では、今のカレンダー(新暦)ではなく“旧暦”を使っていました。
旧暦では7月・8月・9月が「秋」とされ、その真ん中――つまり8月15日が“中秋”です。
その夜に見えるお月さまを特に「中秋の名月」と呼んで、大切にしてきたのです。
月を眺める文化
中秋の名月には、昔から月見団子やススキをお供えする風習があります。
ススキは稲の穂に見立てて、豊作を願う意味が込められています。
また、まんまるなお団子は「これからも豊かに暮らせますように」という感謝と祈りのしるしです。
月の中のウサギ
お月さまの模様が「ウサギが餅をついているように見える」というのも、日本ならではの言い伝え。
他の国では「人の顔」「かに」「ライオン」など、さまざまな見え方をするそうです。
同じ月でも、見る人の文化によって感じ方が違う――それがまた面白いですね。
まとめ
-
“中秋”は旧暦で“秋のまんなか”という意味
-
月見団子やススキを飾るのは、豊作への感謝のしるし
-
お月さまのウサギは日本独自の見立て
たまには夜空をゆっくり見上げてみましょう。
昔の人たちのように「きれいだね」と言葉を交わす時間も、立派な“まいぺーすの学び”です。