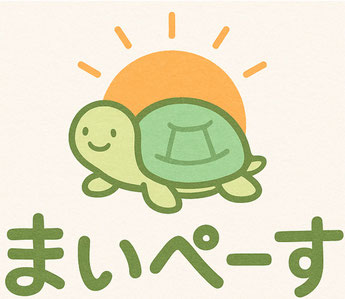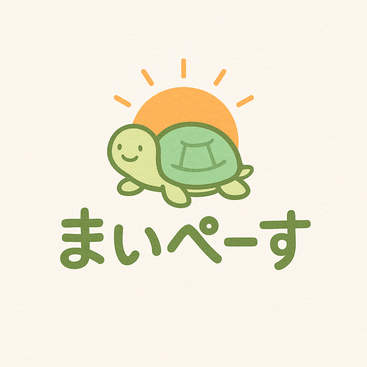
「テスト」と聞くと、なんとなく緊張してしまう人も多いですよね。
けれど、もしテストが“クイズ大会”のようなイベントだったら、ちょっと楽しそうだと思いませんか?
クイズのように考えると
クイズ大会では、間違えても「え〜そうだったの!?」と笑える雰囲気があります。
失敗が恥ずかしいものではなく、「次は当てたい!」という前向きな気持ちにつながります。
テストもそんな気持ちで取り組めたら、もっと楽しくなるかもしれません。
出題者の視点になってみよう
テストを「出される側」から「出す側」に変えてみると、勉強の仕方がぐっと変わります。
自分で問題を作ってみると、
-
どんな部分が大事か
-
どう聞かれるとわかりやすいか
が見えてきて、自然と理解が深まるんです。
たとえば歴史なら「この人はどんなことをした人?」、英語なら「この単語を使って質問を作ろう」など。
“クイズを作る勉強法”は、まさに遊びながら学ぶ方法のひとつです。
大学受験レベルになると、むしろこの「出す側」の立場に立って考えることが大事だったりもします。
学びを“イベント”に変える発想
テストも宿題も、「やらなきゃ」ではなく「どう楽しもうか」と考えると気持ちが軽くなります。
まいぺーすでは、そんな“学びを楽しむ発想”を大切にしています。
学ぶことを「勝負」ではなく「イベント」にできたら、子どもたちは自然と伸びていきます。
まとめ
-
テストを“クイズ大会”のようにとらえると気持ちが前向きに
-
出題者の視点に立つと理解が深まる
-
「どう楽しむか」が学びを続ける力になる
勉強って、本当はもっと自由で面白いもの。
「問題を解く」だけでなく、「問題を作る」「誰かに出す」ことも、立派な“学び”なんです。
今月も、まいぺーすで“遊びながら学ぶ”時間を一緒に楽しみましょう!